3月26日(日)、いよいよ発表会当日です。
今日は、10:00から11:00まで稽古をし、
11:15からはいよいよ発表会。
午後からは振り返りの会を行っていきます。
ここでは、まず本番前から発表会の様子までをお伝えします。
■稽古~本番前の様子
部員さんたちは10時に集合。
道具の置き位置やスタンバイの場所を確認して冒頭のシーンから振り返っていきます。
舞台裏はこんな感じ。
出る順番で道具が並べてあります
舞台裏にも照明やマイクも仕込んであります
両袖には出る順番が書いてあります
新しく追加した曲を流しながら動いていきます
一昨日、有志の皆さんで録音した曲はプロローグや各部の随所で使われています。
昨日録音した掛け声は、エピローグで実際に皆さんが声出しをする際に一緒に流れます。
あっという間に11時。いよいよ開場です。
配布したパンフレット
お客さんを入れている間、部員の皆さんは楽屋へ。

裏では柏木さんが皆さんを激励していました
さぁ、いよいよ幕が上がります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
■絵からはじめる発表会
プロローグ~天地創造~
一人の人が歩いてくる 手には筆
何もないところに筆を置く すると点が生まれる
何もないところに筆を引く すると線が生まれる
点と線があれば そこに世界が生まれる
第1部 命が生まれ亡びるまで
微生物
深海魚
蚊蜻蛉
鳥
人間が現れる
やりを持つ
発明する
銃を持つ
大きな爆発が起こる
静寂が訪れる
第2部 粘菌人類の誕生と滅亡
色々な菌類
四人の粘菌人類 発酵→増殖→
成長→胞子→
拡散
粘菌人類たち出会う
祭りがはじまる
踊り出す
熱狂の中、突然倒れる
断末魔…
静寂が訪れる
「答えを求めては遠ざかる」
「答えを求めてはならない」
静寂
エピローグ
一人の人が筆を動かす 点と線が現れない
あきらめ? 一人の人は去っていく
しかし
点と線が動く
人は気が付かない
点と線だけの踊り
“ちょちょんが ちょん!”
“ちょちょんが ちょん!!”
道具たちは影になっていく…
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
これにて終演!
12月から積み重ねてきた活動の成果が十分に表れた発表会でした。
「よく最後までたどり着いて、よくこんな訳の分からないことを最後まで堪能してやってくださったなと思っています。出演者の皆さんもそうですし、スタッフ、それから急遽駆けつけてくれた(観客の)皆さんも。」と柏木さん。
午後からは振り返り。
こちらは別の記事で紹介していきます。
まずは皆さん、大変お疲れ様でした!
(マネージャー・まりこ)
* * * * * * * *
講師インタビュー特別編「柏木さんに聞く!」
3月3日の「演劇ワークショップ②」で、柏木さんと辻野こもんのあいだで交わされていた、今回のストーリーラインについてのお話を、改めてお届けします。
(柏木)このワークショップの流れを考えると、絵を描くところから始まってるんですよね。墨汁を一滴垂らすところから「この世界」は生まれている。だから、この「一筆置く」ということが、世界を生み出すビックバンなわけですよ。いってみれば、「点と線を描くよ」ってなった日(12月14日の舞台美術WS)は、もう天地創造の日なんです、僕のなかで。だから、そこから始めるんです。
で、天地創造があって、ある程度形づくられていく、要するに地球が形づくられていくっていうのがオープニング。そこから生命が溢れ出していく。で、人類が生まれて、兵器を生み、だからまあ一回滅ぼそうかなと思うわけですよ。で、また別の形のものが生まれてきちゃった。それもやはり人のようにワアってなるけど、その別の形のものもやはり滅びてしまった。……ってなったときに、「生み出すことになんの意味があるのか」っていう自己省察の時間がくるんじゃないかと思ったんです。
ひとりの人が出てきて、空間に筆を置くっていうところから世界が始まって、でも、何度その世界を起こし、始めても滅んでいくんですよ。そうすると「意味がないんじゃないか」って疑問へ、多分たどり着くんじゃないかと思うんですよ。それは今、「芸術ってなんのためにあるの?」って社会のなかで疑問符を突きつけられている我々でもあると思うんです。で、いろんなことを考えるっていう時間があって、これは最終的にどうなるかはまだ見えてないところもあるんですけど、今のところは、その作品づくりに打ち込んで、「でも意味がないのかもしれない」って問答しつづけたその人が、去っていくっていうことにしようと思っているんです。
だけどそこには、倒れてるかもしれないけれど、生み出したものたちは残っているわけですよ。で、この生み出したものたちはまた再び命を吹き返して、今度は点と線だけで踊り始めるっていうラストにしたいなと思っていて。もしかしたら、創造者は倒れていくかもしれない、けれども、創造したものは残るじゃないかって。瞬間的に生み出されたエネルギーとか物語はなくなっていくかもしれない。でも書きつけられた文字は残るでしょ、楽譜は残るでしょ、録音した音は残るでしょ、フィルムは残っていくじゃないかと。それを新しく見ていく人たちが、また新しく価値をつくっていくんじゃないか。だから、最後その人は消えて、点と線は残り、点と線だけが踊るっていうラストにしようと思ってるんですね。
で、すべては最初に彼ら、参加者の人たちが、筆を置いたところから始まってるんですよ。この物語というかワークショップみたいなものは、ここからが始まりだから、だからそこからシーンを始める。なので、必ず水滴の音がするのは、水と墨によって世界が始まったから。まず水の音が「ぴちょん」ってする……っていうところから、全部のシーンが始まるといいかなって思ってるんですけど。
(辻野)今日も柏木さんが「ダブルミーニング」って言っていたけれど、今の話ってダブルどころかマルチミーニングというか。ワークショップをしているリアルタイムのレイヤーがあって、それが舞台で再びもう一度始まって、終わって。だけどそこでまた、リアルタイムの次元でひとつの結果ができる。結果ができるってことは成果物ができる。成果物ができるってことは、残すってことになる。そこからまた生まれて、また……というように延々と。それって「真理だな」って感じたんです。
(柏木)まあ、ただ勝手に意味を考えていけばいいんですけどね。見てる人たちが見ながら、参加者が参加しながら、「あれはなんだったんだ」「これはどうしてだろう」って考えながら、舞台にのってくれればいいと思うので。で、これが不思議なんですけど、僕、書いたあとに気づいたんですよ。先にないんですよ。「こういうことだからこう書こう」じゃなくて。言ったじゃないですか、無意識に触れないと創作できないんですよ。
……以降の内容は3月3日のインタビューへどうぞ……
で、天地創造があって、ある程度形づくられていく、要するに地球が形づくられていくっていうのがオープニング。そこから生命が溢れ出していく。で、人類が生まれて、兵器を生み、だからまあ一回滅ぼそうかなと思うわけですよ。で、また別の形のものが生まれてきちゃった。それもやはり人のようにワアってなるけど、その別の形のものもやはり滅びてしまった。……ってなったときに、「生み出すことになんの意味があるのか」っていう自己省察の時間がくるんじゃないかと思ったんです。
ひとりの人が出てきて、空間に筆を置くっていうところから世界が始まって、でも、何度その世界を起こし、始めても滅んでいくんですよ。そうすると「意味がないんじゃないか」って疑問へ、多分たどり着くんじゃないかと思うんですよ。それは今、「芸術ってなんのためにあるの?」って社会のなかで疑問符を突きつけられている我々でもあると思うんです。で、いろんなことを考えるっていう時間があって、これは最終的にどうなるかはまだ見えてないところもあるんですけど、今のところは、その作品づくりに打ち込んで、「でも意味がないのかもしれない」って問答しつづけたその人が、去っていくっていうことにしようと思っているんです。
だけどそこには、倒れてるかもしれないけれど、生み出したものたちは残っているわけですよ。で、この生み出したものたちはまた再び命を吹き返して、今度は点と線だけで踊り始めるっていうラストにしたいなと思っていて。もしかしたら、創造者は倒れていくかもしれない、けれども、創造したものは残るじゃないかって。瞬間的に生み出されたエネルギーとか物語はなくなっていくかもしれない。でも書きつけられた文字は残るでしょ、楽譜は残るでしょ、録音した音は残るでしょ、フィルムは残っていくじゃないかと。それを新しく見ていく人たちが、また新しく価値をつくっていくんじゃないか。だから、最後その人は消えて、点と線は残り、点と線だけが踊るっていうラストにしようと思ってるんですね。
で、すべては最初に彼ら、参加者の人たちが、筆を置いたところから始まってるんですよ。この物語というかワークショップみたいなものは、ここからが始まりだから、だからそこからシーンを始める。なので、必ず水滴の音がするのは、水と墨によって世界が始まったから。まず水の音が「ぴちょん」ってする……っていうところから、全部のシーンが始まるといいかなって思ってるんですけど。
(辻野)今日も柏木さんが「ダブルミーニング」って言っていたけれど、今の話ってダブルどころかマルチミーニングというか。ワークショップをしているリアルタイムのレイヤーがあって、それが舞台で再びもう一度始まって、終わって。だけどそこでまた、リアルタイムの次元でひとつの結果ができる。結果ができるってことは成果物ができる。成果物ができるってことは、残すってことになる。そこからまた生まれて、また……というように延々と。それって「真理だな」って感じたんです。
(柏木)まあ、ただ勝手に意味を考えていけばいいんですけどね。見てる人たちが見ながら、参加者が参加しながら、「あれはなんだったんだ」「これはどうしてだろう」って考えながら、舞台にのってくれればいいと思うので。で、これが不思議なんですけど、僕、書いたあとに気づいたんですよ。先にないんですよ。「こういうことだからこう書こう」じゃなくて。言ったじゃないですか、無意識に触れないと創作できないんですよ。
……以降の内容は3月3日のインタビューへどうぞ……
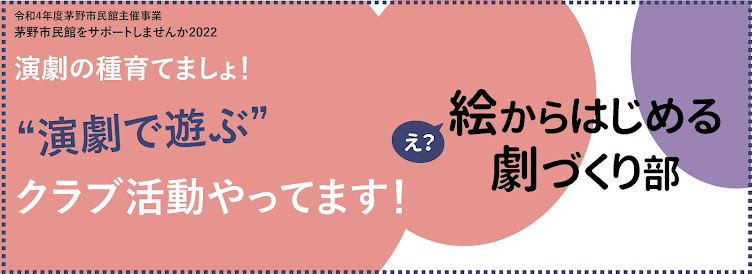

















































































0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。